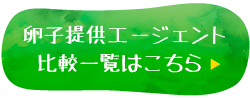公開日: |更新日:
卵子の高齢化と、「卵子提供」の本当の意味
「卵子の老化」は、妊娠を考えている人にとってしばしば問題となるものです。現在は、初婚年齢とともに初産の年齢もあがっていっていますが、そこには依然として避けきることのできない問題があることもたしかです。ただ、同時に、そのリスクを知ることで、早くに不妊治療に踏み切ることができるのも事実です。
ここでは、「卵子の老化(高齢化)とは何か」「卵子の老化が起きるとどのようなリスクがあるのか」、そして最後に、「治療方法(卵子提供)」について解説していきます。
年齢による卵子の減少と老化について
女性の体には、あらかじめ定められた「卵子の数」があります。この「卵子の数」が一番多い時期というのは、いつくらいなのかを少し考えてみてください。多くの人は、「思春期ごろ」「第二次成長期のころ」と考えるのではないでしょうか。
実は、卵子の数がもっとも多いのは、生まれる前、まだ胎児の段階です。3か月~6か月の胎児のときに、すでにその体のなかには700万個ほどもの卵子が宿っています。これはその後徐々に減少していき、生まれた後はその個数が増えることはありません。また、生まれてくるときにはすでに200万個までに減少しています。
この卵子の数は、その後も、加齢とともにどんどん減っていきます。思春期の頃にはそれでも25万個ほど存在していますが、閉経するころにはほとんどゼロに等しい数になっています。
また、卵子の質も低下していきます。妊娠をしにくくなるだけでなく、妊娠したときにも異常が起きやすくなるという特徴を示します。
妊娠率の低下と流産率の上昇
上では、「加齢とともに妊娠しにくくなる」という話をしました。これは、「不妊治療をしたときの分娩率」を見ると分かりやすいでしょう。
34才以下の人の場合、9回の不妊治療を行えば、分娩率は70パーセント程度にまで引き上げられます。対して35才~29シア才の場合は45パーセント程度、40才以上の場合は10パーセント程度の確率でしか妊娠もしくは分娩に至りません。
また、仮に妊娠をしたとしても、その妊娠が継続できるかどうかも年齢によって大きく差が出るという事実があります。
たとえば、25才の場合は流産率は13パーセント程度です。しかし30才になれば15パーセント程度、35才では20パーセントを越えます。40才では35パーセント程度と大きく上昇し、43才以上の場合は妊娠をしたとしても2回に1回は流産してしまいます。
かつて、「高齢出産」といえば、それは「30才以上の初産」を指していました。これが見直され、現在では「35歳以上が高齢出産」と位置付けられています。また、不妊治療も進歩はしています。しかしそれでも、加齢が与える妊娠・分娩への影響は決して小さくはありません。
参考:(PDF)厚生労働省「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」
卵子提供とは何か
「望んでも子どもが持てない」という人のために行われるのが「不妊治療」です。
「高齢によって卵子の質が落ちたり、その数が減少したりするのであれば、卵子を提供してもらえばよい」と考える人もいるでしょう。そのため、「卵子(や精子)の提供による不妊治療」が選択肢として思い浮かぶ人もいるかもしれません。
しかし実際は、この「卵子(精子)提供は、加齢によって子どもを持てない夫婦は、受けることができない」という条件があります。高齢で出産した場合母子ともに危険な状態に陥る可能性があること、養育費の問題があること、そもそも「不妊症」ではないことがその理由です。
もっとも、この「加齢による」という条件の定義づけは明確ではありません。医師の診断によるところが大きいからです。ただ、国では、「50歳以上」というのを一つの目安としています。逆に言うのであれば、それ以下の年齢であるならば、医師の診断によってはこの方法をとることのできる可能性も高くなる、ということです。
子どもがいないこと=不幸せである、ということはだれにも言えません。
しかし子どもを望む夫婦であるのなら、高齢出産のリスクを知るとともに、不妊治療の一つである「卵子提供」にも目を向けるとよいでしょう。
参考:厚生労働省「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」
卵子提供エージェント一覧で比較はコチラ