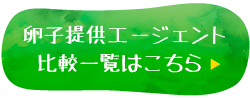公開日: |更新日:
不妊治療にかかる費用はいくら?保険はあるの?
不妊治療は健康保険の適用外?
不妊治療が高額な理由は、健康保険の適用外になる治療があるためです。保険の範囲なら3割の負担ですむ医療費が、全額負担になってしまうため、通常の治療費と比較して3倍以上の費用がかかります。
しかし、全ての不妊治療が保険適用外というわけではありません。2024年8月時点において、日本の不妊治療に対する保険適用はさらに充実しています。現在、保険適用の範囲には、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)といった高度生殖医療も含まれています。年齢制限や治療回数などの制限はありますが、以下の不妊治療が保険適用となります。
- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)
- 高度生殖医療(体外受精、顕微授精)
保険適用となるには夫婦どちらも健康保険に加入している、指定された医療機関で治療を受けるといった条件があります。また、重度の男性不妊の場合は一部の治療が保険適用外となるケースがあるようです。
ぜひ活用したい、自治体の助成金制度
不妊治療にかかる費用の負担を少しでも軽減するために、国や地方自治体が助成金制度を設けています。「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が、国が実施している不妊治療の助成金制度です。地方自治体には、この制度に上乗せする形で独自の制度を設けているところがあります。都道府県ごと、市町村ごとに異なるので、詳細は居住の自治体で調べてみてください。ここでは、厚生労働省が実施している国の制度を紹介します。
大まかにいえば、不妊治療にかかった費用を1回につき15万円まで助成してくれます。ただし、治療の初日時点で、妻の年齢が43歳未満という条件があります。また、助成回数にも制限があり、初回治療時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上だと通算3回までとなっています。
日本国内に住む健康保険に加入している夫婦が対象で、治療開始前に申請を行う必要がありますが、以前の制度と比較して所得制限の条件もなくなり、より助成を受けやすくなりました。
国の助成金は体外受精か顕微受精に限られています。その段階以前のタイミング法などや、卵子提供は対象外になっています。地方自治体の助成金は、適応範囲が異なる場合もあるので、よく調べてみましょう。
地方自治体の助成制度
不妊治療で活用できる制度には、国からの助成金だけでなく地方自治体の補助金もあります。
たとえば東京都では「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」を実施しており、体外受精及び顕微授精を行う場合に「先進医療」に係る費用の一部(全体の10分の7かつ上限15万円)を助成してもらえます。条件として、1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療であること、厚生労働省から実施医療機関として指定を受けている登録医療機関での実施などが挙げられます。
この制度は事実婚の方でも同一世帯であり他の方との婚姻関係がないことを認められれば受けられるため、より間口が広いものとなっています。
参考:東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要/東京都福祉局
不妊治療にも適用できる保険を活用する
自治体の助成金も助かりますが、それでもまだまだ不妊治療の自己負担額は大きなものです。最近では、民間の保険の中に不妊治療が対象になっているものがあります。
加入2年後から、不妊治療の際に1回あたり5〜10万円の保障金を受け取ることができます。
どのような保険なのかをもう少し詳しくみてみましょう。
加入条件と適用範囲
この保険は日本生命から発売されている「シュシュ」という女性向け医療保険です。
加入対象:16〜40歳の女性
保険期間:10〜20年
適用範囲:3大疾病、特定不妊治療と出産祝い金、満期時の一時金
受け取ることができる保険金
がん、心筋梗塞、脳卒中にかかった場合や死亡時に300万円受け取ることができます。不妊治療の有無にかかわらず出産時に祝い金がもらえます。保険期間満期時には200万円(出産祝い金と不妊治療給付金を受け取った場合は差額)を受け取ることができます。
そして気になる不妊治療は、特定不妊治療(体外受精、顕微受精)を行った場合に受け取れます。金額は、1〜6回目までは1回につき5万円、7〜12回目は1回につき10万円で、最大90万円受け取ることができます。
注意点
加入から2年間は不担保期間として、不妊治療の保険金が受け取れません。また出産祝い金も1年後以降でないと受け取ることができません。
「シュシュ」の他には、東京海上日動が不妊治療等補助保険という商品を扱っています。しかし、この保険は個人では加入できず、企業や健康保険組合での団体扱いのみです。お勤めの方は総務部や加入の健康保険組合で確認してみてください。
以上、不妊治療に関する費用と助成金制度、保険について紹介しました。不妊治療は金銭的には、肉体的にも大きな負担を伴います。どの程度までお金をかけてもよいかを、事前によく計画しておくことが大切です。そして、助成金や保険などの活用を検討した資金計画を見積もっておきましょう。
卵子提供エージェント一覧で比較はコチラ