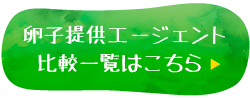公開日: |更新日:
特定生殖補助医療法案について知る
特定生殖補助医療法案とは?
背景と目的:なぜこの法律が必要なの?
体外受精や人工授精といった「生殖補助医療」は、ここ数十年で大きく進化してきました。特に、第三者から提供された精子や卵子を使った治療も増えてきましたが、実はこの分野には大きな“穴”があったのです。
というのも、こうした治療で生まれた子どもと親との法律上のつながりが、きちんと決められていませんでした。病院やクリニックでは、専門団体が出すガイドラインに従って対応していましたが、それだけでは不十分。たとえば「自分がどこから生まれたのか知りたい」という子どもの声にも、しっかり応える仕組みがなかったのです。
こうした問題を解決しようと、2025年2月に「特定生殖補助医療法案」が国会に提出されました[注1]。この法案は、第三者からの精子や卵子の提供を伴う治療に関して、国がしっかり情報を管理・監督することで、患者さん・提供者・生まれてくる子ども全員の権利を守ることを目的としています。
いわば、“ルールのなかった場所”に初めて法律の光を当てようとしているわけです。ただし、この法案には「法律婚の夫婦だけが対象」という制限も含まれており、実際の運用にはさまざまな課題が残されています。
法案の流れといまの状況は?
この法案は、自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党の4つの政党によって議員立法として提出されました。当初はスムーズに審議が始まると見られていました。
ところが、立憲民主党や共産党などの野党から「法律婚の夫婦に限定するのは不公平」「子どもが自分の出自を知る権利が十分に守られていない」などの理由で反対の声が上がり、話し合いはスムーズに進まなくなってしまいました。
6月5日の時点では、法案の本格的な審議入りは見送られることに。そして6月9日には与党の幹部が「今の国会では採決は難しい」と明言。国会の会期が6月22日に終わると、この法案は自動的に“廃案”になる可能性が高くなっています。
対象となる治療について
どんな治療が対象になるの?
この法律の対象となるのは、主に次の4つのケースです。
- 夫以外の精子を使った人工授精(AID)
- 夫以外の精子と妻の卵子を使った体外受精や胚移植
- 夫の精子と、妻以外の卵子を使った体外受精や胚移植
- 代理母が妊娠・出産をする「代理懐胎」
ただし、これらの治療を受けられるのは、あくまで「医学的に自然妊娠が難しいと医師が判断した法律婚の夫婦」に限られています。事実婚のカップルや同性のカップル、独身の女性は対象外とされており、この点が大きな議論を呼んでいます。
また、対象外の人に対してこれらの治療を提供した場合、医療機関には罰則が科される可能性があり、病院やクリニックにとっては非常に慎重な対応が求められます。
その結果、日本国内で治療が受けられない人たちが、海外の医療機関に頼ったり、インターネットなどを通じて個人で取引したりするケースも出てくると懸念されています。こうした現実をふまえて、「本当に今のままでいいのか?」という声も強く、今後、対象範囲の見直しが大きなテーマになっていくと考えられています。
法案ではどんなルールが決まっているの?
医療機関や仲介機関は「許可制」に
この法律では、第三者の精子や卵子を使った治療を行う病院やクリニックは、国(厚生労働大臣)の許可が必要になります。また、精子や卵子を提供してくれる人を紹介する“あっせん機関”も、内閣府に登録しなければいけません。
許可を得た医療機関は、提供者との面談や健康チェック、採取から移植までの流れをきちんと記録して、定期的に報告する義務があります。これを無許可で行った場合、最大で懲役3年または300万円以下の罰金という重い罰則があるんです。
これまでのように「医療機関の自主判断に任せる」スタイルから、「国がしっかり管理する」仕組みに変わることで、安全性や透明性は高まります。ただ一方で、特に小規模なクリニックや大学病院などでは、費用や手続きの負担が増えてしまうため、地域の医療体制への影響も心配されています。
提供者や家族の情報は100年間保存
提供者(ドナー)、治療を受けた夫婦、生まれた子どもに関するデータは、国立成育医療研究センターが一括して管理します。その保存期間は、なんと原則100年間。かなり長い期間ですよね。
保存される情報には、提供された時期、採取の方法、ドナーの年齢や血液型、身長などが含まれます。センターはこれらの情報を管理するだけでなく、問い合わせに対応する窓口の役割も担います。
ただし、これほど多くの個人情報を長期にわたって保存するとなると、情報漏えいやシステムの老朽化といったリスクへの備えも必要になります。また、当事者が自分の情報を見たいと希望したときに、スムーズで丁寧な対応ができる制度にしておかないと、仕組み自体が形だけになってしまうという懸念も出ています。
子どもが「自分の出自」を知ることはできる?
この法律では、提供された精子や卵子で生まれた子どもが18歳になったら、自分が提供型治療で生まれたかどうかを確認できるようになります。そのうえで、ドナーに関する基本的な情報(名前以外)を知ることもできます。
さらに、もしその子どもが「ドナーに会いたい」と希望した場合は、研究センターが間に入ってドナーに連絡を取ってくれます。ドナーが同意すれば、名前を含む情報も開示される仕組みです。
ただし、親に「告知しなさい」という義務はなく、ドナーが情報開示に同意しない限り、名前などの情報は明かされません。これについては、国連が求める「子どもが出自を無条件で知る権利」とは違いがあるとして、当事者団体からは「子どもの権利が軽く扱われている」といった声も上がっています。
営利目的は禁止、違反すれば高額な罰金も
この法律では、精子や卵子をお金で売買したり、広告を出して提供を募ったりすることは禁止されています。商売として仲介することもNGです。
違反した場合、法人には最大1億円、個人でも最大500万円の罰金が科されます。提供者に対しては、交通費や仕事を休んだ分などの「実費だけ」が支払われることになっており、お金目当てでの提供を防ぐ仕組みになっています。
しかし、日本ではもともとドナーが少なく、さらに提供が減るのではないかという懸念もあります。あまりに厳しすぎるルールは、逆に違法な“闇取引”を助長してしまう可能性もあるため、今後は広報や支援なども組み合わせて、柔軟に運用していくことが求められそうです。
法案への批判とこれからの課題
「出自を知る権利」が十分に守られていない?
この法案では、ドナーの名前などの情報は、本人の同意がなければ、たとえ子どもが成人しても知ることができません。これに対して、「出自を知る権利が十分に保障されていない」として、当事者や人権団体から強い反発の声が上がっています。
たとえばイギリスでは、2005年にドナーの匿名性を完全に廃止し、子どもが18歳になると無条件でドナーの氏名を知ることができる仕組みが導入されました。オーストラリア・ビクトリア州では、出生証明書に「第三者の提供による出産であること」を記載し、親が子どもに事実を伝えることを後押ししています。
こうした国際的な流れと比べると、日本の制度は「慎重すぎる」「子どもの権利を最優先にしていない」との指摘が根強くあります。
対象となる人が限られている点への疑問
この法案で治療を受けられるのは、法律上結婚している男女のカップルだけです。つまり、事実婚のカップルや同性カップル、独身の女性は対象外となってしまいます。
この制限については「家族の形は多様なのに、それを認めない制度だ」との批判が強くあります。また、治療を受けられない人が海外のクリニックに行ったり、非公式なルートを使ったりすることで、安全性や健康管理の面で問題が起きるのではないかと心配されています。
医療機関にとっても、対象外の人を診ることで罰則のリスクがあるため、対応をためらってしまう可能性があり、「人権も医療の安全もどちらも損なわれる」といった懸念の声が広がっています。
倫理面・社会面での心配なポイント
この法案では、提供者や子どもの情報を100年間保存するという、とても厳しいルールが設けられています。これは透明性を高めるという面では良いことですが、万が一情報が漏れてしまった場合の影響はとても大きいものになるでしょう。
また、ドナーが提供後にしっかりと健康管理や心のケアを受けられる仕組みが整っていない、という点も指摘されています。何回まで提供していいのかという回数制限も、はっきりとは決まっていません。
さらに、商業的な行為への厳しい罰則が導入されたことで、逆に非合法な“地下取引”が活発になってしまう恐れもあります。
こうしたさまざまなリスクに対応するには、倫理委員会と国の監督機関がしっかり連携し、副作用や社会的な影響を継続的に見守っていく体制づくりが欠かせません。
この法案、今後どうなるの?世界と比べて見えてくる課題とは
今回の国会では成立見送りの見通し
2025年6月上旬、与党の幹部から「今の国会ではこの法案の成立は難しい」という発言がありました。このことから、6月末の会期終了までに採決されず“廃案”になる可能性が高まっています。
もし廃案になれば、今ある法案は一度白紙に戻り、次の国会で新たに提出し直す必要があります。その際には、法案の内容を見直し、与野党で再び話し合いの場を設けることが求められます。早くても、年内に審議が始まれば良い方だと言われています。
この分野にはこれまで法律がなかったため、制度の空白期間が続くと、医療現場や当事者にとって不安や混乱が広がる恐れがあります。一日も早く、そして丁寧に議論を進めることが望まれています。
海外はどうしてる?世界と比べた日本の現状
海外では、日本よりも早くこの分野の制度整備を進めてきた国が多くあります。
たとえば、イギリスではドナーの匿名性を2005年に廃止。子どもが18歳になれば、ドナーの名前を知ることができる制度を導入しました。オーストラリアの一部地域では、出生証明書に「精子や卵子の提供で生まれたこと」が記載され、親が子どもに事実を伝えやすくする工夫もされています。
また、スウェーデンでは1985年から無条件でドナーの氏名が開示される制度があり、ドナーに対して心理的なサポートを受けられる仕組みまで法律で整えられています。
一方、日本の制度案では、個人情報の保存期間(原則100年)は世界でもトップレベルですが、情報開示の範囲や治療を受けられる対象が限られているなど、国際的なスタンダードとはズレがあると言われています。
まとめとこれからのポイント
現時点での制度の限界を理解することが第一歩
現在の「特定生殖補助医療法案」では、治療を受けられるのは「法律婚の夫婦」のみに限定されています。そのため、事実婚のカップルや、独身女性、同性カップルは対象外となっており、日本国内で公的に認められた治療を受けることは難しい状況です。
これは法的な“空白地帯”がようやく埋まろうとしている一方で、多様な家族の在り方にはまだ対応しきれていない現実でもあります。
対象から外れている場合、海外のクリニックを選ぶ人もいます。ただし、国によって制度や安全基準、ドナー情報の管理方法は大きく異なります。費用も高額で、サポートが十分でない国もあるため、渡航医療を検討する際には、実績のある専門のエージェントに相談したうえで検討しましょう。
卵子提供を検討する女性は増えていますが、制度や倫理、家族の理解など、ひとりで抱え込んでしまいがちな悩みも多い分野です。そんなときは、当事者コミュニティやカウンセラー、医療機関の相談窓口を頼ってください。